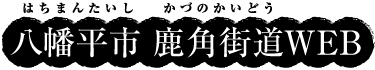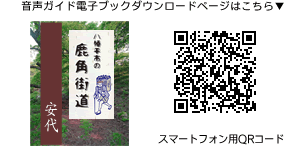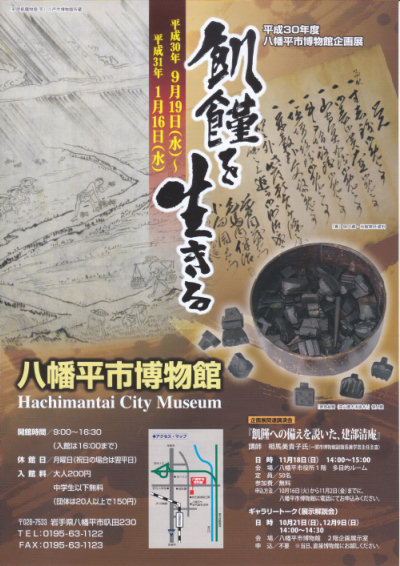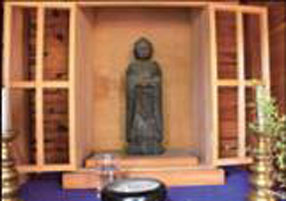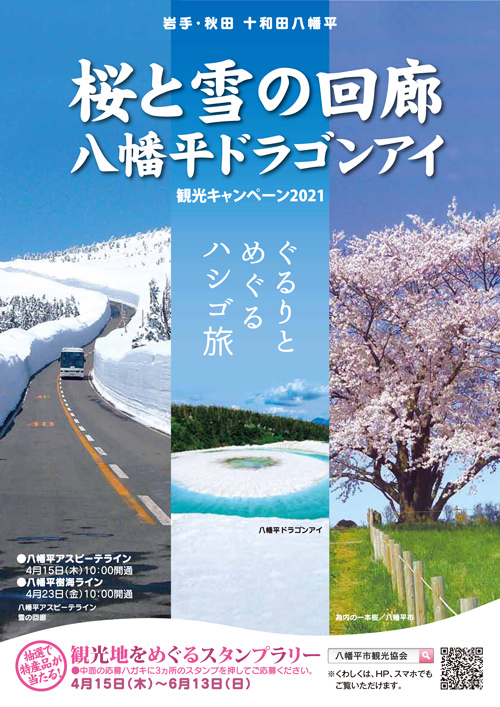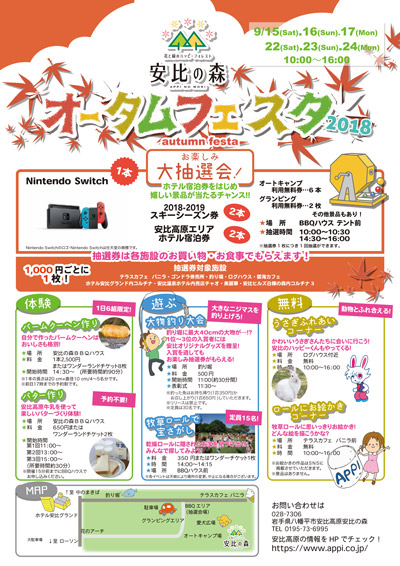荒屋八幡神社の鰐口
鰐口とは、仏堂の正面軒先につり下げられた金属製梵音具(仏具)の一種で、鋳銅や鋳鉄製のものが多く、鐘鼓を二つ合わせた形状で鈴を扁平にしたような形をしています。上部に上からつるすための耳状の取手が左右にあるほか、下側半分の縁に沿って細い開口部と金の緒と呼ばれる布施があり、これで鼓面を打ち誓願成就を祈念しました。鼓面中央は撞座と呼ばれ圏線によって内側から撞座区、内区、外区に区分されます。荒屋八幡神社の鰐口の外区には、「奉掛八幡大菩薩御宝前成田氏安之尉生年十二歳敬白」と享保十九年(1734)の銘が刻まれています。奉納したものと考えられますが、由来などの詳細は不明です。■寸法:直径17㌢(鋳銅製)


|
名称
|
荒屋八幡神社の鰐口
|
|
よみ
|
あらやはちまんじんじゃのわにぐち
|
|
分類
|
仏像等
|
|
所在地
|
荒屋新町152番地1
|
|
指定状況
|
市指定文化財(歴史)
|
|
年代(年)
|
1734
|
 このページを印刷する
このページを印刷する